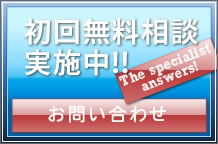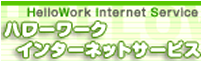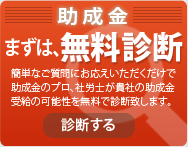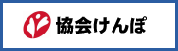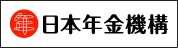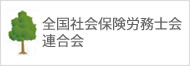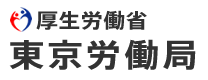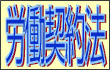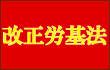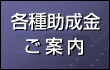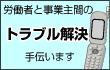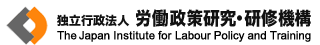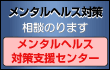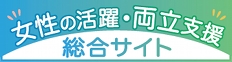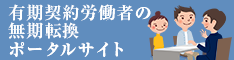作成日:2013/04/30
生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方
生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する論点
1.高齢者が活躍できる場(地域側ニーズ)の掘り起こし
○ 地域で高齢者が活躍できる場として、子育て、介護周辺の生活支援サービス、農業等が指摘されているが、高齢者をマンパワーとして活用しうる分野や地域課題はどのようなところにありうるか。また、それをどのようにして掘り起こし、ビジネスとして成り立たせることはできるか。
○ 地域の企業において、これまで培った知識・技能を発揮し、高齢者が就業できる場はどのようなものがあるのか。
○ 高齢者の特性に応じて就業機会を発掘することが必要であると考えるが、その手法としてどのようなものが考えられるか
○ 例えば、これまで1つの仕事、1人の仕事とされていた業務を切り分けるなど、「ちょっとした仕事」「スポット的な仕事」を見付けることも就業機会の確保につながると考えられるが、これを効果的に行うには何が必要か。
2.地域で活躍したい高齢者側の視点(高齢者側のニーズ)
○ 高齢者は退職後の社会参加活動に何を求めているか。とりわけ、就業という形での社会参加に何を求めているか。高齢者が社会参加するメリットは何か。
○ 高齢者の高い能力と就業意欲を地域課題の解決のために活かすためにはどのような仕組み(対象となる高齢者を掘り起こす仕組み等)が求められるか。
○ 地域に出て行くために高齢者自身がなすべきこと又は改善すべきことは何か。また、高齢者自身が就業機会に適応し、溶け込めるよう変わるために支援機関ができることは何か。
3.高齢者が活躍できる場と活躍したい高齢者の結び付け
○ 高齢者が活躍できる場(地域側ニーズ)と、活躍したい高齢者(高齢者側のニーズ)を結び付けるためにどういったものが必要か。
○ 一方、このような機能を担う仕組みを新たに設ける場合には、どのような形態や位置付けが考えられるか。既存の仕組みとの棲み分けや連携のあり方はどうあるべきか。
○ 地域側のニーズと高齢者側のニーズを結び付けるために、例えばプラットフォーム的なものを設置し、コーディネーターを配置することも効果的と考えられるが、プラットフォームやコーディネーターに求められる役割・能力はなにか。また、コーディネーターを発掘・育成するためには、どのような支援が必要か。
○ 民間の活用方法としてどのようなものがありうるか。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030tix.html